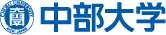58. フォルクローレ
今から200年前、南アメリカ解放の父として知られるシモン・ボリバルの活躍により、スペインからの独立を勝ち取った国は彼の名前にちなんで、ボリビアと名付けられました。そのボリビアの大都市ラパスはアンデス山脈の標高3700mのところにあり、そこで活躍する日本人音楽家を中心とするグループの演奏会が名古屋でありました。
自分の首から下げた長さの違う筒を3列に並べて作られたサンポーニャを、南アメリカ大陸に見立てて、年長の浩安さんが、ボリビアの位置を示されました。そうするとサンポーニャが何となく南米大陸の形に見えてきました。太平洋沿岸に沿って連なるアンデス山脈。南米大陸の中央に位置するボリビア。北と東はブラジル、南はアルゼンチン、南東はパラグアイ、南西はチリ、北西はペルーに隣接しています。四方を海で囲まれている日本とは対照的に、五つの国によって囲まれているのです。
「4人アンデス」。健一さんがマンドリンのような形のチャランゴを弾きながら、高い陽気な音を出し、踊りまわります。19年間もボリビアに住んでいて、映画の音楽演奏も手掛ける広行さんがギターを奏でながら、スペイン語で民族音楽を歌い上げます。康平さんがギターを弾いていたかと思うと、次の曲ではチャランゴ、そして次の曲では山羊の爪をたくさん結び付けて、手で振って独特の音を出すチャフチャスを演奏します。私の最も好きなのは浩安さんの吹くサンポーニャの音色。ハーモニカのように吹くものの、いかにも南米の雄大な自然が思い浮かんでくる深い音色です。浩安さんは尺八のような縦笛ケーナも吹き、大太鼓ボンボも叩きます。
「コンドルは飛んでいく」は、滅びたインカ帝国の魂に向かって大空をコンドルが飛んでいくという、哀愁を帯びていながら、大自然を感じるので、私の好きな曲です。アンデスの音楽を聞きながら、陽気なボリビアの人たちの生活を想像します。国民一人あたりのGDPでは日本の10分の1にもならない国だけれど、陽気な人たちを思い、心の豊かさを感じずにはいられませんでした。



サンポーニャは南米大陸の形に似ていた。ボリビアの位置はその中心にある。
4人アンデスはテンポの速いボリビアの民俗音楽を演奏する。右から浩安さん、康平さん、広行さん、健一さん。