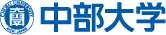57. 大学入学共通テスト
「大学入試」という言葉から、大学生にとってはついこの間まで頑張って勉強した事を思い出すのではないでしょうか。人生100年と言われるなかにあっても、どの大学で教育を受けるかということが個人にとっての大きな選択となることでしょう。
大学入学試験は、今から40年前、当時の文部省が「現在の入試は受験生に受験技術的学習を強い、高校以下の教育に大きな影響を及ぼしている」という考え方に基づいて、機会均等、公平・公正さを重視して、共通一次が導入されました。その11年後に大学入試センター試験、そしてこれから予定されている大学入学共通テストへと変遷しています。今回、文部科学省は新制度の下で導入しようとしていた、英語民間試験活用の延期を発表しました。延期の理由として民間試験活用が内包する地域格差、経済格差が挙げられました。中部大学では前もって、今回の活用を見送ることを決定していましたが、延期の発表は社会に大きな波紋を投げかけています。
アメリカの例を見ながら今後の日本の入学試験の在り方を考えてみましょう。アメリカの大学では民間試験であるSATやACTと言った共通(標準)テストの点数を入学判定に用い、高校の成績や課外活動などが考慮され、アドミッションオフィスで入学が決定されてきました。長く、共通テストこそ、フェアな選抜方法と考えられてきたのです。しかし近年、複数回受験できる共通テストは経済的に豊かな層に有利に働き、経済的理由が教育格差を生み、高等教育機関における多様性が阻害されていることが認識されています。全米で共通テストの点数の提出を義務付けない大学が広がりを見せています。アメリカには約3000の4年制大学と約1600の2年制大学が存在していますが、現在有力大学を含めて1000以上の大学で共通テストスコアの提出は任意であるとしているのです。
アメリカの大学で入学者選抜に学力だけでなく、課外活動などの側面を取り入れるようになったのは、20世紀前半のことです。ヨーロッパで排斥されていたユダヤ人が移民としてアメリカに入ってきて、学力試験の成績で上回るユダヤ人学生が急速に増えてきたために、多様性を確保するという理由で総合的評価が導入されたといわれています。また人種差別やマイノリティーの問題を解決するために、大学選抜においてもアファーマティブ・アクション(積極的な差別是正策)が取られてきました。一方、2018年に入学選考を巡って、ハーバード大学が、SAT高得点のアジア系米国人を差別しているとして訴えられました。その裁判の判決が、この10月に出ました。ハーバード大学の主張する「学業の優秀さ以外の幅広い選考基準を用いることの正当性」の主張が認められたことになります。アメリカでも教育改革が進行中ですが、注目に値する判決結果だと思います。
中部大学では総合大学として、門戸を広げ、意欲のある多様な才能を受け入れています。講義や実習を通して基礎学力を確認しながら、適性と意欲を見るAOポートフォリオ入試を導入しています。そして教え育てるという上から目線ではなく、個々の才能が見出されて、大きく育つような、学びを中心とした教育環境を作り上げています。