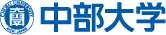62. 観瀾―波を見る
新型コロナウイルス感染症は世界中に広がり、街の中では多くの人がマスクを着用していることに異様な雰囲気を感じます。グローバル化が進行するにつれて、拡散のスピードが速まるようです。
過去のいくつかの感染症の例を見ると、風土病として一地域に限定されていたものが、交通手段の発達とともに地域が拡大していくことがわかります。2世紀の古代ローマ帝国ではローマ街道を通って天然痘やマラリアが広がり、14世紀にはシルクロードを通ってヨーロッパに入ったペストが猛威を振るい、19世紀には産業革命による交通手段の発達がコレラを世界的な流行に導いています。20世紀に入ると第1次世界大戦中にスペイン風邪と呼ばれたインフルエンザが世界中に広がり、当時の世界人口18億人に対して、死者は5千万人とも1億人ともいわれています。
日本でも疫病は古くから「はやりもの」、「はやりやまい」といった言葉で恐れられてきました。東大寺の大仏は「はやりやまい」や社会不安を鎮めるために作られたとも伝わっています。感染症の正体がわかってきたのは近代になってからのことです。驚異的な感染力を持つウイルスは、ドイツ語のヴィールス(Virus)からきており、医学用語として明治時代に入ってきました。それまでにも江戸時代に、蘭学の一部として西洋医学は入ってきており、医学を含む自然科学、人文科学等さまざまな新しい概念や知識が翻訳されて入ってきています。
私の専門である物理学は、蘭学の中では自然科学一般の中に含まれていました。江戸末期にはオランダ人ボイスの自然科学の教科書をもとにして、『気海観瀾(きかいかんらん)』が翻訳出版されています。気海観瀾は空気、海、見る、波を表す4文字です。瀾はあまり見慣れない字ですが「人生、波瀾万丈」と言ったように使われており、この場合「瀾」は大波を意味しています。気海とは地球を包む空気の広がりを海に例えた言葉で、自然界ともいうべき意味です。思いつくままに「気」の付く言葉を並べてみても、大気、空気、天気、気象、電気、磁気、気体そして病気があります。『気海観瀾』では自然界の現象、物質の性質も扱われています。観瀾とは波を見るという意味です。書名は一般物理学講義といったものではなく、『気海観瀾』という見事な日本語に置き換えられていると思うのです。
今や気海では、グローバル化という言葉で表されるように、人間の往来はより活発となり、そして人間の親交がより密となり、お互いがすぐに影響を受けることになります。今回の新型コロナウイルスの拡がりは、グローバル化した人間社会を気海に例えるならば、気海に現れたさざ波のようにも感じます。ただし場所によってはそのさざ波は大波、いやそれどころか津波のように押し寄せてもいるようです。
この100年間、世界の人口増加は約57億人で、その前の100年の人口増加約8億人に比べると非常な勢いで増えていることが分かります。世界中で健康管理や衛生が行き届くようになり、医療が進み、感染症に対しても有効な手段が取られてきた事も人口増加の一因と考えられます。今回の感染症に対しても有効な対策が見出されて、津波を制御して平常の気海に戻ってほしいものと思いつつこれを書いています。