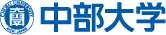63. 多様性―みんなちがって、みんないい
明治期に、先人は西洋の言葉を適切な日本語に置き換えて、西洋の文化を日本の文化の中に取り入れてきました。例えば「社会(society)」、「自由(freedom)」、「人格(person/personality)」、「哲学(philosophy)」等々、新しい概念が訳語とともに入ってきて、日本の文化に溶け込んでいきました。
その訳のためにもともとの概念が正確に伝わらなかった例もあります。たとえば、「教育」を考えてみましょう。Educationの訳は当初「教化」「開発」などが使われていましたが、初代文部大臣の提唱した「教育」が広く使われるようになったのです。
Educationは語源的には「引き出す」、つまり個人の持てる才能を見出して、引き出すという意味があります。「教育」という言葉だと、上から目線で知識を教え、師あるいは社会が考える望ましい姿に学生を育てる、ということになるのではないでしょうか。学生は師の教えをそのまま受け入れることが前提で、「望ましい姿に育てる」という場合には学生個人の視点や才能を育てて成長を促すという考え方に欠けているように思います。
福沢諭吉は「文明教育論」(1889年)の中で、「教育」の訳語を非難しています。
「学校は人に物を教うる所にあらず、ただその天資の発達を妨げずしてよくこれを発育するための具なり。教育の文字はなはだ穏当ならず、よろしくこれを発育と称すべきなり」
私はアメリカに留学し、その後カナダとアメリカの大学にいる間に、日本の教育に対して福沢諭吉の言葉と同じような感覚を持っていました。そこで、「教育」という言葉に、日本の文化の中で新しい解釈を加えていく必要があると思っています。中部大学における教育では、個人の才能を見出し、引き出していくことを目指したいと思っています。あくまでも見出すのは個人であって、教員は学生と共に学びながら、個人が自らの才能を見出すための環境を整えるだけなのです。
授業を飛び出して、学生は自分たちで企画してチームで学ぶ例もあります。たとえば、つい先日のことですが、人文リテラシー「映像を読む」では映像文化について学んだあと、一つの学生チームが学長室に来て、私にインタビューをして、それを映像にまとめ、授業の中で自分たちの作品を示し合って議論しています。工学部の学生を中心とした「Hack U中部大学」では、学んだプログラミングとデザインを自分たちで実践し、学生チームの企画によるオリジナルな作品を作り、成果を発表し合います。国際関係学部では専門の異なる教員を交えて、分野横断・学年縦断の議論形式の「ハイブリッド・プロジェクト」が行われています。議論に加わり自分の意見を話すためには、前もって課題に関連した基礎知識を自ら習得していなければなりません。教員においてもグローバル化する社会、科学技術の急速な進展といった情勢の中で、絶えず学び続けることが求められています。
話題を転じて、大学と多様性という言葉に着目してみましょう。日本では明治期に欧米諸国の制度を参照しながら学校制度として大学・中学・小学を定めましたが、「大学」という言葉は奈良時代から官僚養成機関として存在した「大学寮」に遡ることができそうです。英語では大学のことはuniversityと言い、ラテン語のuni(one、一つ)とvertere(turn、回転する)に起因する言葉です。色々な物がぐるぐる回りながら一つになっていくイメージです(turn into one)。世界最古のユニバーシティとして知られるボローニャ大学は、学びを共にする集団によって作られています。色々な学問分野の人たちが集まって一つになるところ、すなわち総合大学というわけです。日本の中にすでに存在した「大学」という言葉が、欧米の「university」という言葉に当てはめられた例でしょう。日本における大学のこれからのあり方を考えるときに、世界のユニバーシティが今どうなっているのかを知ることは意味がありそうです。
ユニバーシティと似た言葉にダイバーシティ(diversity)が有ります。これはラテン語のdi(aside、横に)とvertereからできているので、色々な物がぐるぐる回りながら一つ一つ飛び出していく(turn aside)と言うところでしょうか。ダイバーシティは多様性と訳されます。
日本では古来、自然界に存在するすべての物の存在と人間を、つながりのある物として考えてきました。最近使われ出したバイオダイバーシティ(biodiversity、 生物多様性)よりも、地球上にあるすべての存在に対して、等しく多様性を見出していました。中日新聞の社説に金子みすゞの詩のことが書かれていました(1月26日「国語で叫ぶ、勿体無い」)。「わたしと小鳥と鈴と」を引用します。
「わたしが両手をひろげても、 お空はちっとも飛べないが、
飛べる小鳥はわたしのように、 地面をはやくは走れない。
わたしがからだをゆすっても、 きれいな音は出ないけど、
あの鳴る鈴はわたしのように、 たくさんなうたは知らないよ。
鈴と、小鳥と、それからわたし、 みんなちがって、みんないい。」
そこには自然界に存在する命あるものと、命なきものをすべて包み込んだ多様性を受け入れるようすが感じられます。
地球上の存在は、必ずしも命あるものと命なきものに分けられるものでもないようです。新型コロナウイルスが現在猛威を振るっていますが、ウイルスは生物と似た構造を持つものの、細胞がなく、自力で動くことも増殖することもできないことから、命あるものとはいえないでしょう。まさに地球上に存在するものの多様性をあらわすような存在です。
総合大学では、様々な背景と異なる価値観と考え方を持った、高等教育機関にふさわしい学生・教員・職員が集まり、まさに多様性のあることが基本となります。ダイバーシティのあることがユニバーシティの本質といえるでしょう。中部大学では自然に恵まれた教育環境の中で、すべての教職員と学生が、優しさを持って多様性を受け入れる、そんな教育をしたいと思っています。