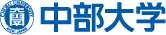88. 学事暦
ようやく緊急事態宣言も解除されました。しかし、まだ安全のために春学期中は遠隔授業を続けますが、6月1日から実験や実習のために、学生さんが登校を始めます。遠隔授業が始まって3週間、今のところトラブルもなく授業が運営されています。新たな試みから、高等教育における学びについての在り方を考えるきっかけとなることを期待しています。
新型コロナウイルス感染症が再び感染拡大の方向へ向かわなければ、中部大学における春学期は8月に終わり、9月末には秋学期がはじまります。しかし、緊急事態宣言が解除され、外出自粛規制が解かれても新型コロナウイルスは絶滅したわけではなく、現在季節が逆の南半球で感染症が拡大していることを思えば、警戒を怠るわけにはいきません。
感染拡大による休校長期化により、学年の始まりを9月にすればどうかという議論も起こっています。そこで今日は学年の始まりの時期、終わりの時期といった学事暦(学年暦)ということに思いを巡らせてみようと思います。
まず歴史的なことをおさらいしておきましょう。江戸時代には寺子屋の入学時期や進学時期は特に決まっていたわけではなく、いつでも入学でき、能力に応じて進級もできたようです。それでも習慣としての入学時期は、初午(はつうま)つまり立春後の最初の午の日ということで、春先の行事だったようです。江戸川柳でも初午が枕詞として使われ、「初午はまず錠前を覚えさせ」(子供が寺子屋に通い始める初午には、まず戸締りのことを覚えさせる)などと詠まれていたそうです〔毎日新聞2020.2.29〕。
明治の末、1908年に書かれた夏目漱石の「三四郎」では、東京帝国大学に9月に入学するために、熊本から東京に向かう小川三四郎が出てきます。このころ小学校や旧制中学校では4月入学、旧制高校や帝国大学は9月入学でした。1886年に発足した帝国大学は、ドイツ・イギリスの制度に倣って作られたため、9月入学となっていました。
宮崎駿監督の映画「風立ちぬ」では、東京帝国大学に入学して飛行機にあこがれた堀越二郎が、夏休みの帰省先から東京に戻る列車の中にいるときに、関東大震災に遭遇する場面が出てきます。大震災は1923年9月1日のことで、その2年前に帝国大学は4月入学に変わり、小学校から大学まですべて4月入学となっていました。
歴史を辿れば、日本の学制における4月入学は、国の会計年度や徴兵制度における徴兵時期に関連して決まっていったようです。一方、世界の大学に目を向けてみると、長い夏休み休暇のあとに新学年が始まることが多く、北半球にある多くの欧米諸国では6月~8月の夏休みの後の8月末から9月に入学時期があり、そして南半球にある南米諸国やオーストラリアなどは12月~2月の夏休みの後、2月末から3月にかけて入学時期になっています。南半球でも北半球でも、暑い夏は仕事に適さない時期と考えてのことでしょう。その点、日本は4月を入学時期として、夏休みを学年の途中に挟んだ独特の学事暦を持っているといえます。学期の切れ目ではあっても、学年の途中であるだけに、夏休みの期間もそれだけ短くなっています。しかし、中部大学ではいくつかの研究科では、秋入学も実施しており、社会人や留学生を受け入れています。
11世紀に設立されたイタリアのボローニャ大学より以前に存在した、エジプトのカイロにあったアル・アズハル大学では入学随時、受講随時、退学随時という3信条があったそうです。江戸時代の寺子屋の学びのスタイルに通じるものを感じます。今は失われた授業時間を取り戻すために、スケジュール調整に追われていますが、コロナ禍が収まったところで、ポストコロナの高等教育は遠隔教育を通して得たICT活用のみならず、高等教育の在り方そのものについても変革の時を迎えることでしょう。高等教育における学びは、自分を見つめながら自分の持てる才能に向き合う必要があります。そのためには夏休みに限らず、まとまった時間が必要で、自由に物事を考え、自らの興味のままに時間を使って自らの才能を見出し、伸ばしていくことが大切となるでしょう。
ポストコロナと言っても、北半球の多くの国で外出禁止などの行動制限が段階的に解除される一方、新型コロナウイルス感染症は南半球に広がり、さらに拡大傾向にあるようです。我々は一部ではあっても、6月から学内での対面授業を開始しますが、くれぐれも対策を怠ることなく慎重に授業を進めていきたいと思っています。