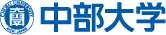91. バッタの相変異
2019年後半以降、東アフリカでバッタが大発生し、コロナ禍と時を同じくして、東アフリカ発で、繁殖を繰り返しながら中東を経て、南西アジアにまで拡大しています。バッタの大発生は10年以上前に関西国際空港の草原で起こっていたりして、日本でも昔からよく知られています。空を覆うほどのバッタの大群の襲来は、黒い悪魔として恐れられ牧草地と耕地が蝗害被害を受け、食糧危機を引き起こします。東アフリカでは現在第3波のバッタ襲来に警戒しているということです。
氷は温度が上がると水となり、さらに温度が上がると水蒸気となります。このような物質の状態の変化は固相、液相、気相という『相転移』と言われていますが、生物にも相変化のように同じ種が環境の変化によって変わることがあると知られており『相変異』と呼ばれています。通常野原で見かけるバッタは緑色で、集団で見かけることはないのですが、大発生時に見られる黒っぽくて小さく羽が長いバッタは、緑色のバッタから環境の変化によって生まれることが、100年ほど前から知られていました。
バッタの生態は単独で育てば、おとなしく緑色で『孤独相』と呼ばれる一方、集団で育てば荒々しい性格を持ち巨大な群れを作る『群生相』になることがあります。幼虫のころに仲間の数が増えて互いに触れ合ったり、仲間の姿を見ることによる刺激を受けると、成長しても体が小さく黒っぽくて性格も一変して凶暴になり、群生相が出てくるということです。最近の研究では、バッタの脳にあるコラゾニンというペプチドホルモンが『相変異』を起こしているということがわかってきました。普通のバッタがたくさん集まって過密状態になり、お互いに接触すると体の色が緑から黒に変化して、集団行動をとるようになり、食糧がなくなれば大群として空を飛び移動し始めるというのです(「混みあうと黒くなるトビバッタ」管原他、化学と生物、2016)。
私がカナダの中西部に住んでいたころ、夏の3ヶ月を東京で共同研究をすることになり、井の頭線に乗って毎朝超過密の満員電車で通いました。1週間も経たないうちに高熱を出し体に震えが来て、医者の往診を受けたことがあります。理由は満員電車というストレスに対する体の拒否反応だろうと医者は言いました。7年の間北米の田舎町で、大勢の人が物理的に接触するといったことのないのんびりした環境で過ごしてきたために、体が拒否反応を起こしたのでしょう。
最近のコロナ禍で大都市圏に新型コロナウイルス感染者が集中している現実を見るに付けて、都市部における人口の過密状態が気になります。首都圏に日本の総人口の約40%が集中し、東京都の人口密度は全国平均の約20倍にも達しています。2008年以降人口が減少に転じる中、東京周辺にのみ人口が集中するのは、バッタの相変異を連想させる異常事態と感じずにはいられません。そういえば大都市圏に住む人々の中には、イライラして性格が荒々しくなる人も目立つようになった気もします。コロナ禍で、人々が大きなストレスを抱える今、日々心身の健康維持に心がけていきたいものです。