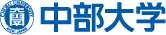85. 学びたいことを見つけよう!
中部大学ではいろいろな形で学生の皆さんの学業、生活面等のサポートをしています。その一つに指導教授制度があり、学生には一人ずつ指導教授がつき、困ったことや悩みの相談に乗っています。学期が終わると、指導教授から報告が届き、今学生の皆さんが何を悩んでいるかを知る機会となります。
「学んでいる内容が自分の興味とは違っている」という学生さんの悩みもあり、思い出したことがあります。
中部大学の元教授が、姉妹校オハイオ大学で教えていた時の学生の話です。彼は最初学んでいる物理学が自分の興味とは違っていると感じ、悩んでいました。学ぶことを放棄せず、その後生物学を学び、物理学を構造生物学に応用しました。その学生ラマクリシュナンは、ノーベル化学賞(2009年)を受賞しました。興味を持てなかった分野と興味を持っていた分野が、新たな分野の発見につながった例と言えるでしょう。
オハイオ大学卒業生の彼は、現在、英国王立協会のCOVID-19専門家グループの議長を務めています。新型コロナウイルスがもたらすパンデミックの解決策を見つける仕事に携わっています。

オハイオ大学のドーム状の屋根を持つロタンダは本学との友好のシンボルになっています(ブログNo.79)。